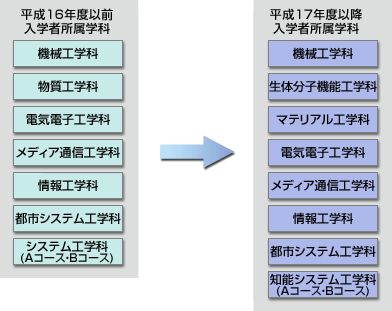学部・学科の沿革
機械工学科の沿革
- 1939年
- 多賀高等工業学校の機械、原動機械の2学科として設置される
- 1944年
- 多賀工業専門学校と改称
- 1949年
- 茨城大学誕生。機械工学科(50)、原動工学科(50)、電気工学科(60)、金属工学科(40)
初年度入学者は158名 - 1956年
- 原動工学科が機械工学科と合併
- 1966年
- 機械工学第二学科新設
- 1968年
- 大学院工学研究科修士課程機械工学専攻の設置
- 1970年
- 大学院工学研究科修士課程機械工学第二専攻の設置
- 1990年
- 機械工学科と機械工学第二学科が合併して現在の機械工学科誕生
定員は90名 - 1993年
- 3年次編入制度開始
大学院博士後期課程生産科学専攻の設置
それに伴い、修士課程が博士前期課程機械工学専攻へ - 1995年
- 工学研究科が理工学研究科へ変更
- 1998年
- 数理感性工学独立講座を機械工学専攻に増設
- 2004年
- 国立大学法人茨城大学工学部機械工学科となる
- 2005年
- 定員を85名に変更する
- 2006年
- 日本技術者認定機構(JABEE)から5年間の認定を受ける
- 2011年
- 日本技術者認定機構(JABEE)から6年間の認定を受ける
- 2018年
- 日本技術者認定機構(JABEE)から6年間の認定を受ける
茨城大学工学部の沿革
茨城大学工学部は、その前身である多賀高等工業学校の創設以来、約70年の伝統を有しています。日本の技術立国としての成長と発展の歴史は、本学の科学技術分野における教育と研究の歴史でもあります。この70年間、今日の科学技術を支える数多くの技術者や研究者を世に送り出してきました。その輝かしい歴史に誇りと自信を持ち、一方では時代の要請に応じてタイムりーに変身しつつ、工学部は発展を続けてきました。
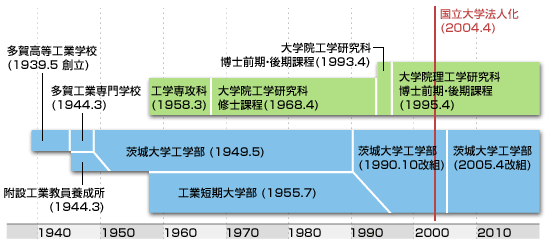
平成17年度に改組を行い、7学科から8学科になりました。